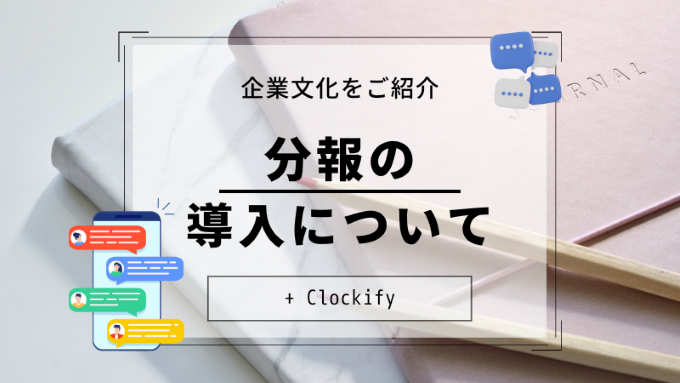はじめに
分報という言葉を聞いたことがありますか?日報や月報というのは一般的によく使われている言葉かと思います。
弊社では分報をとりいれており、今回は分報について記事を書いてみたいと思います。
分報とは
一般的に分報とは以下のようなことを言います。
弊社では、以下のように説明しました。
分報運用の目的
新型コロナウィルス感染症をきっかけに、テレワーク主体となった昨今、社内のコミュニケーションの希薄を課題と感じている会社さんは少なくないのではないでしょうか。
コロナ禍以前は皆がオフィスへ集まって仕事に就き、独り言を放てば誰かが反応してくれたり、ディスプレイを見れば何をやっているのかがおおよそ見当がつき、Enterキーをたたく強さにより「あぁ、何かうまくいってないんだろうなぁ」と察して声をかけることもできました。
また、何やら集中していて声をかけづらいような状況でも休憩に席をたった瞬間を見計らって声をかけたりすることも可能でした。
しかし、テレワーク主体となるとなかなかこういったコミュニケーションがとりづらい状況であるということが弊社でも判明しました。
この状況を現在取りえる手段で合理的かつ経済的に非同期コミュニケーションで解決する方法を模索した結果、分報にたどりつきました。
レンジャー分報のガイドライン
分報の投げ先はSlackに社員全員分の分報用チャンネルを作成しました。
- 各自全員の分報用チャネルに参加(全員の状況を把握できるようにする)
- 通知は基本的にオフでOK(みたい時にみる、非同期で良い状態)
- 本日実施するタスク
- タスクの進捗状況
- 休憩の入り、戻り
- タスク進行にあたり困った/困っていること、最終的にどのような解決方法をとったか
- 上記に付随するコードやConfig、ログの断片
- タスクの進行にあたり参考にした情報、URL
- 現在のテンション
- その他思考の断片、思い付きのネタ
分報を導入してから
上記ガイドラインを全社員へ説明を行い実際に導入しましたが、なかなか全員が行うということはありませんでした。
そもそも呟くのが苦手だ、とか、忘れてしまうとか、そういった声もありました。
この時点では分報として未熟ではあり、分報をいれていいね、などのような声はあまり聞こえてきませんでした。(2022年5月)
自走した組織を目指して
弊社は「自走した組織」を目指していろいろな取り組みにチャレンジしています。
過去に自走型組織を目指すための手段としてコーチングの基礎研修も全社員で受講しました。
 自走型組織を目指すための手段「コーチング」
自走型組織を目指すための手段「コーチング」 自走した組織に必要なことは何か?を考えた時にセルフマネジメントという言葉にいきつきます。
また、この頃、勤務形態の見直しも同時に入っており、どの時間帯に働くか・どういったペースで働くか・勤務時間の管理をどうるすかを考えたときに、やはり各自が当事者意識をもってセルフマネジメントをすることが必要だとなりました。
逆にいうと、以下のことができるようになれば働き方にも裁量をもたせることが可能となるのではないかという考えに至ったのです。
- 誰が何をしているのかがわかるようになる
- 個人の成果・プロジェクト採算性の可視化
この1つ目の「誰が何をしているのかがわかるようになる」ための手段として、「分報」の利用を考えました。また、プロジェクトの採算性をはかるためにも「誰が何に何時間使ったか」を知る必要があるということでこちらは日々入力している工数をいかに正確にいれるか?というところが論点でした。
この2つをかけあわせたときに、タイムトラッキングツールから各々のSlackの分報チャネルに通知が送信されれば、リアルタイムに誰が何をやっているのかがわかる&工数を正確に近い形で入力することができるのではないか、ということでClockifyというツールのトライアルが始まりました。
上記でも少し記載していますが、Clockifyはタイムトラッキングツールのひとつです。ストップウォッチ状のUIでタスクごとの作業時間を計測します。
あらかじめ自分が使用するプロジェクトを登録しておき、開始時に開始ボタンを、終了時に終了ボタンをクリックするだけでそのプロジェクトにかかった時間を記録することができます。
ただ、工数をいれるための工数がふえてしまっては元も子もありません。
トライアルの時点ではクロキファイで記録された各データを工数管理ツールに手動で登録するというプロセスをふんでおりましたが、やはりこれが自動で転記されることがツールを導入するうえでの重要なファクターとなっていました。
ツール導入のトライアルを終え、社員へアンケートをとり、改善点といくつかの運用課題を残しつつも、2022年12月、Clockifyの導入がレンジャー会を経て決定いたしました。
Clockifyを導入して
この頃には自分でつぶやく分報もある程度定着をして始めており、Clockifyを導入してさらに定着化が進みます。
1日の分報チャネルは以下のような形で流れています。
- 1日の予定を書く
- タスクAのClockifyをスタートする
- Slackのチャネルに自動投稿される
- タスクAのClockifyをストップする
- タスクBのClockifyをスタートする
- タスクBのClockifyをストップする
・・・繰り返す - 1日の終わりに終了を呟く(終わりますとか終了とか閉店ガラガラとか・・・)
- 工数管理ツールへ連携するSlackコマンドをただく
- 工数が登録される
この流れで「誰が何を」ほぼリアルタイムで知ることができ、テレワークの課題であった相手の状況がわからず話かけずらい、何の案件・どんな内容で困っているか分からないなどのコミュニケーション課題もかなり解消されてきており、オープンになったよね、とか何をしてるかがわかるからいいよね、といった声は少しずつ聞こえ始めてきました。
さいごに
弊社は文化は自分たちで作り上げていくとし、課題に対して全員で取り組み、トライアンドエラーを繰り返し文化形成をしています。
採用ページでは社員インタビューなども公開しております。当社に興味を持たれた方はぜひご連絡いただければ幸いです。